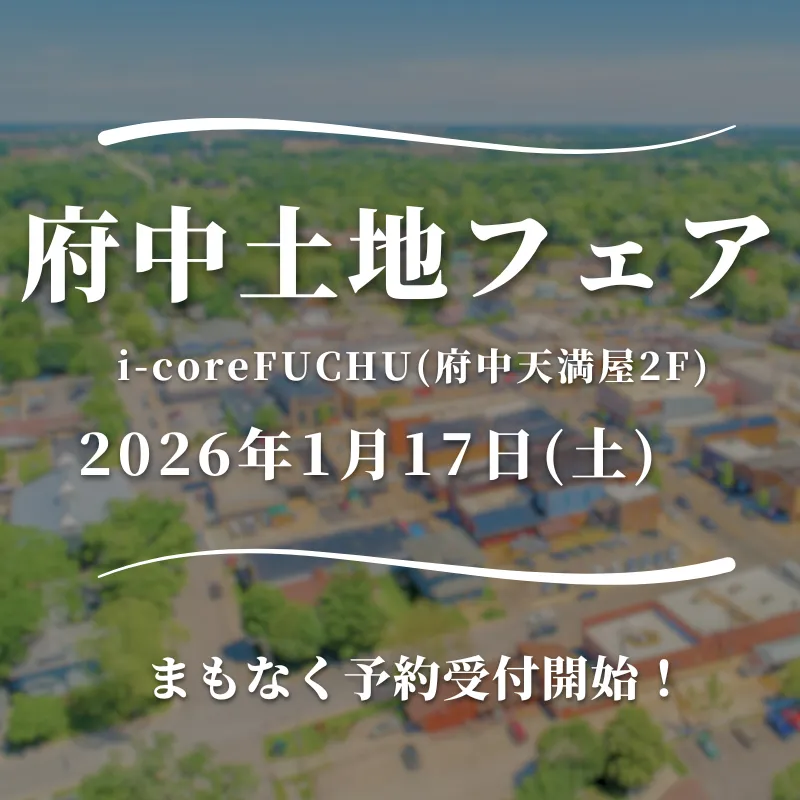
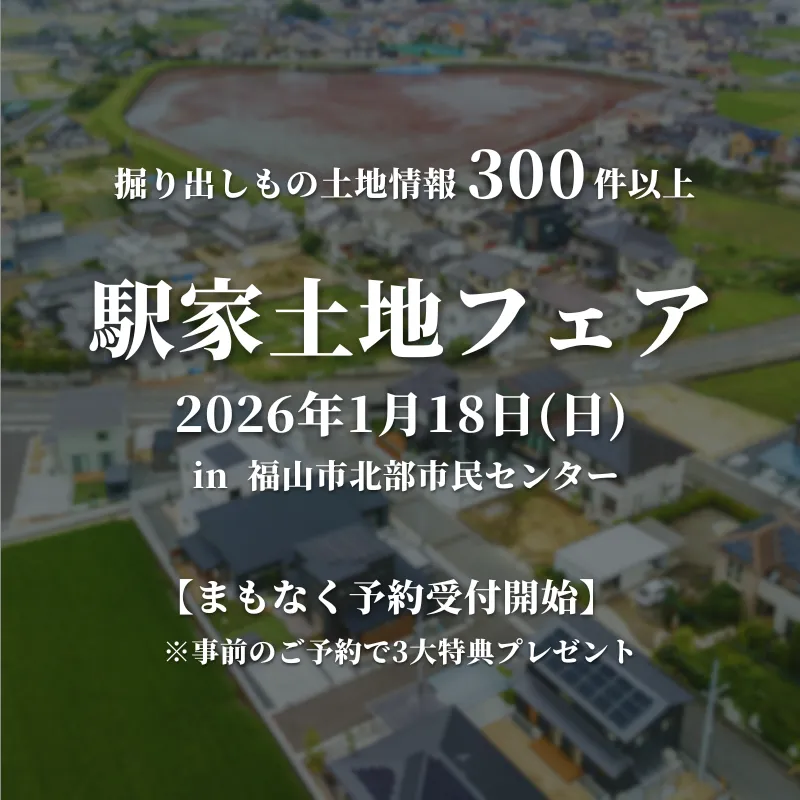
ブログ記事が動画になりました!
(※ブログ記事の内容を家づくりコンシェルジュが動画で分かりやすく解説しています。ぜひ、こちらの動画でご覧ください)
50代になると会社での立場や収入などにおおよその目途がつくので、マイホーム購入を検討を始める人もいますよね。
現在住んでいる戸建が、子どもの独立によって広さや部屋数が必要なくなり、住み替えを考えるのも50代になってからが多くなります。
一方で、50歳から住宅ローンを組んで、本当に返せるのか不安になる人もいますよね。
そこで本記事では、50代の住宅ローンをシミュレーションしてみました。
50代からの住宅ローンをよく理解して、返済と貯蓄のバランスがとれた無理のない計画を立ててみましょう。
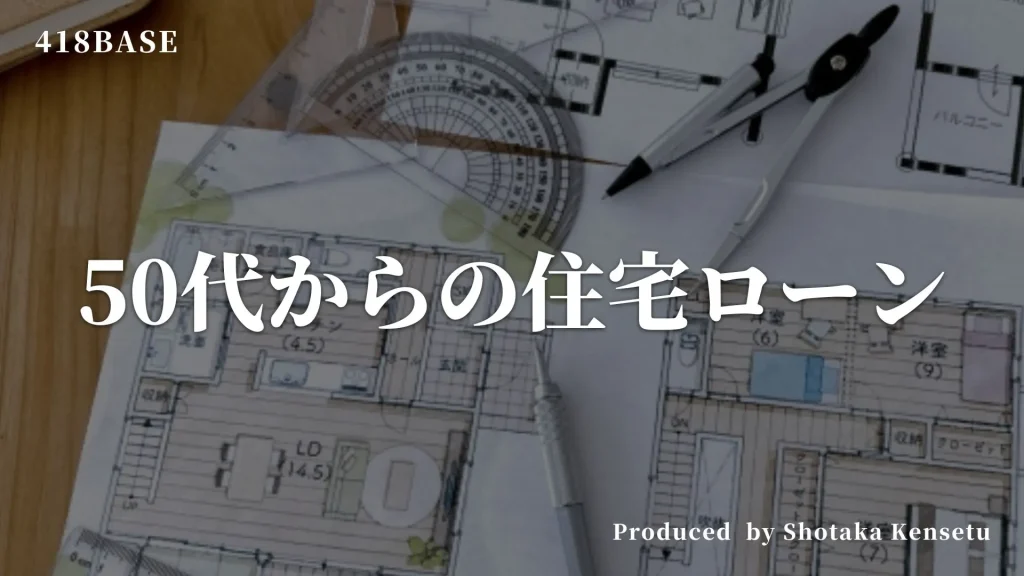
住宅金融支援機構が2022年にフラット35利用者に行った調査では、住宅ローンを組む割合は子育て世代の30代〜40代がもっとも多い結果となりました。(※1)
ですが、実は50歳代も15.6%おり、30歳以下よりも多いことがわかっています。
また、近年は晩婚化などの影響により、住宅ローンの借り入れ平均年齢は42.8歳となっています。
住宅ローンの借り入れをしている年代は、イメージよりもやや高めの年齢層が中心で、50代の利用も一定数あると考えられます。
このような現状から、50代は住宅ローンが通らないというのは噂に過ぎないといえるでしょう。
住宅ローンの審査では借入時の年齢も対象になりますが、健康状態や勤続年数、年収なども影響するため、若いからといって必ず通るものでもありません。
住宅ローンの借入の基準や上限額については、こちらの記事を参考にしてください。
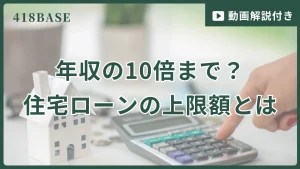
(※1)住宅金融支援機構『2022年度 フラット35利用者調査』
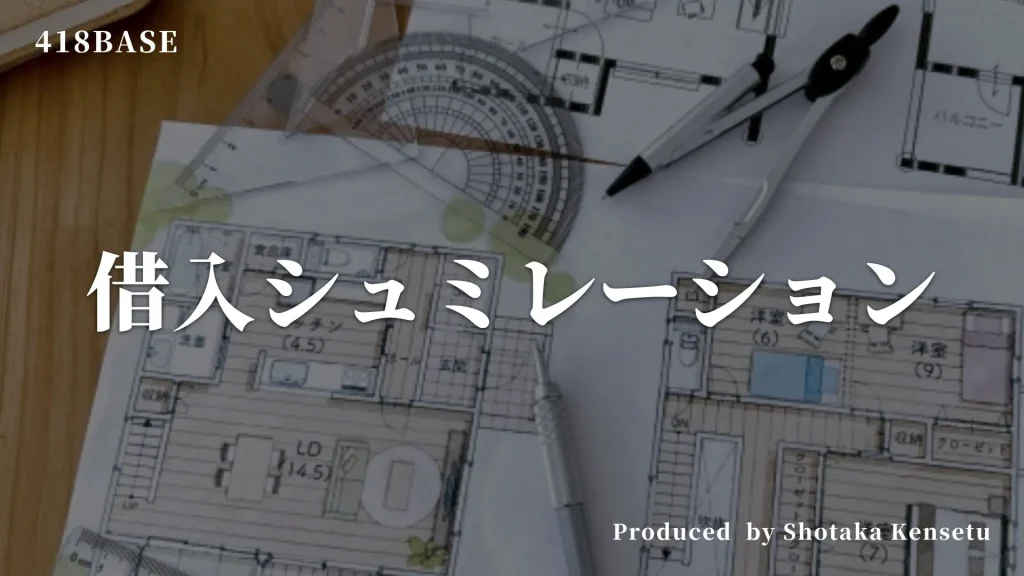
50代でも住宅ローン大丈夫そうだなとは言っても、実際にいくら借入ができるのか不安な人もいますよね。
ここでは、下記の条件で年収別の借入可能額と毎月の返済額をシミュレーションしてみました。
| 年収 | 借り入れ可能額 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| 300万円 | 2,002万円 | 75,000円 |
| 400万円 | 3,115万円 | 116,600円 |
| 500万円 | 3,894万円 | 145,800円 |
| 600万円 | 4,673万円 | 175,000円 |
ただし固定金利よりも、変動金利のほうが金利が低いのが一般的です。
上記は固定金利での計算であり、変動金利の場合は0.4〜0.5%となっているので、毎月の返済額は減ります。
また、住宅ローンは全期間固定金利や、全期間変動金利のタイプだけではありません。
1%前後が多い、10年固定金利の後に変動金利に移行するタイプ、10年固定後に再度固定を選ぶか変動にするか選べるタイプなど複数あります。
金利のタイプや銀行によっても変わってくるので、シミュレーションは、あくまでも目安として参考にしてくださいね。
金利のタイプについて詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。
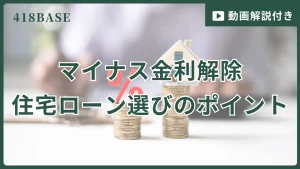

50代は、会社勤めをしている人は定年が見え始め、老後の生き方や暮らし方を模索するタイミングです。
そんなときに、「人生でもっとも高い買い物をするなんて無謀すぎる」と悩んでしまいますよね。
ここでは、50代からの住宅ローンが無謀ではない3つの理由を紹介するので、それぞれについて詳しくみてみましょう。
住宅ローンの借り入れ年齢の上限は、金融機関によって差はありますが、多くの場合80歳となっています。
50歳で住宅ローンを借りる場合、80歳から51歳(※)となり、最長で29年間の返済期間が確保できます。
住宅ローンの返済期間は30年前後が多いので、たとえ50代であっても返済期間自体は平均と変わらないことがわかりますね。
(※)数ヶ月の経過を考慮して、1歳上乗せで計算
50代の住宅ローンの審査が厳しくなるのは、借り入れ申し込み時の年齢が50歳だからではありません。
完済時が高齢になるため、それまでしっかりと支払い能力があるかを見られているからです。
頭金を多く入れて返済額を減らしたり、75歳や70歳で返せる金額の借り入れ額であったりすれば、無理のない範囲の返済額であると判断されやすくなります。
50代であっても、完済できると判断されれば審査は問題なく通るでしょう。
30代と比べて、50代は支出を抑えられることも、住宅ローンが無謀ではない理由です。
近年は子どもの大学進学率が上がり、多くの家庭で学費が重い負担となっています。
30代の子育て世代の場合、住宅ローンと学費の二重の返済となるケースもありますよね。
一方で、子どもが大学を卒業して就職している50代であれば、学費の負担はありません。
また、子どもが独立するなどして生活費がコンパクトになるタイミングでもあるので、30代と比べると日常生活の支出も下がります。
50代は30代よりも年収が高く、支出を抑えられることから、住宅にかける資金が増えるのでローンが組みやすくなります。
50代で住宅ローンを組むメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。
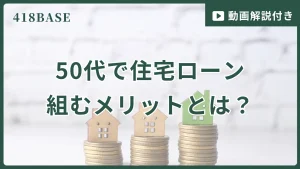

50代で住宅ローンを組むと、30代のように現役で働ける期間が長くありません。
定年前に完済を迎えるのが難しい面もありますよね。
現役で働いていても役職定年などで、収入が前年よりも下がってしまう可能性もあります。
また、50歳から上限の29年の返済期間を設定すると、途中からは年金からローンを支払うことになります。
収入が下がったときや年金暮らしになっても支払い可能な返済額を設定し、再雇用や再就職も含めた完済計画を現役時代にしっかりと立てておくことが大事です。

繰り上げ返済とは、毎月決まって行っている返済とは別に、借り入れ残高の一部(または全額)を返済することをいいます。
繰り上げ返済によって、返済額の軽減や返済期間の短縮ができるメリットがあります。
これだけを聞くと、「繰り上げ返済はどんどん行うべき」と思いますよね。
しかし、50代の場合は住宅ローンと平行して、老後資金やリフォーム代、医療費などを準備しておく必要があります。
貯まったお金を次々に繰り上げ返済に使ってしまうと、いざというときにお金が足りなくなってしまう可能性があるので、貯蓄の分はきちんと用意しておくことが大事です。

50代の住宅ローンについて紹介してきましたが、「まだ家づくりは先かな」と考えている人はピンときませんよね。
では、50代で家づくりをしようと考えるタイミングはいつなのでしょうか。
下記などの理由から、50代は二世帯住宅や同居を考えることが多いタイミングになります。
また、若いときのように体が動かない年齢に差し掛かってくるため、動ける今のうちに老後を見据えて暮らしやすい家に住み替えたい、建て直したいという人も多いですね。
20代や30代とは違った気持ちで、50代からのマイホームを検討する人が増えています。
50代からの家づくりと性能スペックの必要性については、こちらの記事を参考にしてください。
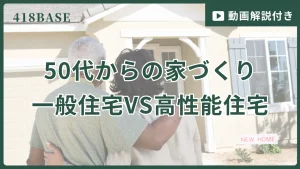
418BASEは広島県福山市・府中市・三原市・世羅町を中心に、備後地方の家づくりをサポートする会社です。
これまで地域の方々からたくさんのご支持をいただき、創業から50年以上を迎えることができました。
418BASEでは、高気密・高断熱の注文住宅の設計・施工を行っており、最新設備を取り揃えたモデルハウスも公開しています。
備後地方で家づくりを検討されている方は、ぜひ418BASEへご気軽にご相談ください。
50代の住宅ローンの年収別シミュレーションや、50歳で家を建てるときの住宅ローンの組み方について解説しました。
最後に、この記事をまとめます。
住宅の購入のベストタイミングは人によって違うため、50歳で自分の家を持ちたいと思ったらそのときがあなたにとって最適なタイミングといえるでしょう。
住宅ローンを組む前に不安や悩みを解消し、無理やリスクのない返済計画を立てて、自分らしい人生を過ごす「我が家」を手に入れてください。
418BASE/昇高建設株式会社 〒726-0023 広島県府中市栗柄町418
モデルハウス・完成物件の見学や資料請求などお気軽にご相談ください。